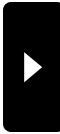2019年02月21日
◆コヤスノキの保全活動
みなさん、西日本の一部の地域にしかなく、兵庫県の指定天然記念物になっているコヤスノキ(子安の木)を知っていますか。
以前、かつてコヤスノキ叢林があった矢野町森の磐座(いわくら)神社を安産信仰の神様として取り上げたことがありました。(http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e254240.html)
今、その磐座神社のコヤスノキが危機的状況にあります。それで貴重なコヤスノキを守ろうと立ち上がった人たちがいます。兵庫県みどりのヘリテージマネージャーの方々です。2月17日に現状調査をされるということで同行させてもらいました。

ヘリテージマネージャーの方々
今、磐座神社にあるコヤスノキは神社境内にある5本のみとなっています

神社の入り口近いところから、1番目のコヤスノキ

茎が、ケモノ(シカ?)によって皮がはがされています

その隣の2番目のコヤスノキ

こちらもやられています。どうも囲いが必要のようです

その下に種が落ちて小さな葉っぱが出ていました
これを生かすべくブロックで囲んでいます

神社の中に入っていって3番目のコヤスノキ。もう元気がありません

4番目のコヤスノキ。さらに元気がなく

枯れかけのようです

宮を挟んで反対側、座光石の横にある5番目のコヤスノキ

完全に枯れていました

幹にはカビが
このままでは貴重な磐座神社のコヤスノキは絶滅してしまいます。そこで、現在は平成28年より国の森林総合研究所でこの5本のコヤスノキの枝を切ってさし木をし、DNAを残す動きをしています(5番目の木はダメだったようです)。そして、ある程度育てばその一部をまた磐座神社に戻し、かつてのような貴重な姿を取り戻そうとしています。
その前に本当にこの地で育つのか、平成29年より実験的に他地のコヤスノキの苗を植え、生長を確認しています。大丈夫のようですね。順調に育っているようです。



計画では、2020年に森林総研で育った苗木を神社周辺に戻す予定です
こ
以前、かつてコヤスノキ叢林があった矢野町森の磐座(いわくら)神社を安産信仰の神様として取り上げたことがありました。(http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e254240.html)
今、その磐座神社のコヤスノキが危機的状況にあります。それで貴重なコヤスノキを守ろうと立ち上がった人たちがいます。兵庫県みどりのヘリテージマネージャーの方々です。2月17日に現状調査をされるということで同行させてもらいました。

ヘリテージマネージャーの方々
今、磐座神社にあるコヤスノキは神社境内にある5本のみとなっています

神社の入り口近いところから、1番目のコヤスノキ

茎が、ケモノ(シカ?)によって皮がはがされています

その隣の2番目のコヤスノキ

こちらもやられています。どうも囲いが必要のようです

その下に種が落ちて小さな葉っぱが出ていました
これを生かすべくブロックで囲んでいます

神社の中に入っていって3番目のコヤスノキ。もう元気がありません

4番目のコヤスノキ。さらに元気がなく

枯れかけのようです

宮を挟んで反対側、座光石の横にある5番目のコヤスノキ

完全に枯れていました

幹にはカビが
このままでは貴重な磐座神社のコヤスノキは絶滅してしまいます。そこで、現在は平成28年より国の森林総合研究所でこの5本のコヤスノキの枝を切ってさし木をし、DNAを残す動きをしています(5番目の木はダメだったようです)。そして、ある程度育てばその一部をまた磐座神社に戻し、かつてのような貴重な姿を取り戻そうとしています。
その前に本当にこの地で育つのか、平成29年より実験的に他地のコヤスノキの苗を植え、生長を確認しています。大丈夫のようですね。順調に育っているようです。



計画では、2020年に森林総研で育った苗木を神社周辺に戻す予定です
こ
タグ :コヤスノキヘリテージマネージャー
2018年04月12日
◆朝日新聞に「感状山城跡」の記事が掲載
先日(4/3)、朝日新聞の地域面で播磨地域の史跡等を紹介する「はりま歴史探訪」に
「感状山城跡」が取り上げられていましたね。
「はりま歴史探訪」では、これまで矢野町に関わるところでは、確か「矢野荘」や「犬塚」が掲載されていました。
「矢野荘」→ http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e393077.html
「犬塚」 → http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e413493.html
感状山に登ると眼下に矢野町が一望でき、矢野町を身近に感じます。(ここに城ができたのも納得)
では、その記事をご紹介しましょう。

(画像をクリックすると大きくなります)
こ
「感状山城跡」が取り上げられていましたね。
「はりま歴史探訪」では、これまで矢野町に関わるところでは、確か「矢野荘」や「犬塚」が掲載されていました。
「矢野荘」→ http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e393077.html
「犬塚」 → http://yanochohiroba.tenkomori.tv/e413493.html
感状山に登ると眼下に矢野町が一望でき、矢野町を身近に感じます。(ここに城ができたのも納得)
では、その記事をご紹介しましょう。
(画像をクリックすると大きくなります)
こ
2012年10月18日
◆森の黒獅子
10月14日は、矢野で残りの集落、森と二木の秋祭りでした。
森の磐座神社に寄らせてもらったときには、ちょうどお祭りが終わったところでした。
にもかかわらず、森には、珍しい黒色の獅子頭があるということで、わざわざお宮を開けてくださり、その獅子頭をその場所に置いて見せてくださいました。
現在は、残念ながら獅子の舞手がおらず獅子舞は行われていないようですが、かつては宵宮でかがり火に照らされたその黒獅子はかっこよく、獅子舞はすばらしかったそうです。






なにか荘厳な重みを感じますね
こ
森の磐座神社に寄らせてもらったときには、ちょうどお祭りが終わったところでした。
にもかかわらず、森には、珍しい黒色の獅子頭があるということで、わざわざお宮を開けてくださり、その獅子頭をその場所に置いて見せてくださいました。
現在は、残念ながら獅子の舞手がおらず獅子舞は行われていないようですが、かつては宵宮でかがり火に照らされたその黒獅子はかっこよく、獅子舞はすばらしかったそうです。






なにか荘厳な重みを感じますね
こ
2012年08月31日
◆福田眉仙石碑設置
(奥は瓜生の八柱神社)
すでに各紙新聞にも紹介されましたが、8月26日に瓜生公民館の入り口に郷土が誇る画家 福田眉仙の生誕地石碑が相生市政70周年記念事業の一環で設置されました。当日は、ご子孫や来賓を招いて除幕式がありました。
眉仙は、以前にも紹介しましたが、東の横山大観と並んで、西の福田眉仙と称されながら、私利私欲のない「無欲の画家」で、後年中央画壇を離れ芦屋で描きたい絵をひたすら描き続けました。そのため全国的に知名度はありませんが、お世話になった方々に数多く作品を残されています。(そこがまたかっこいい)

除幕式の様子(写真提供:橋本一彦氏)

福田眉仙の生誕地石碑

ということで、相生市は市政施行70周年・眉仙没50年記念「福田眉仙展」を9/6(木)~9/27(木)相生市民会館で開催します(ただし14(金)と25(火)は休館日)。どうぞ足をお運びいただいて、郷土の偉人にお会いください。詳しくは下の画像をクリック。チラシが開きます。
こ
2012年06月29日
◆キヌガサタケ
瓜生羅漢さんの「里の店」の方に、「キヌガサタケが出てるので見る?」って言っていただいたので、連れて行ってもらって見せていただきました。
キヌガサタケは、日本では「コムソウタケ」とも呼ばれているそうで、絶滅危惧種にも指定されている大変珍しいキノコだそうです。胞子は他のキノコと違って虫が運ぶそうです。
初めて見ました。感動です!!!
自然の造形美っていうんでしょうか。レースのスカートをはいています。
「キノコの女王」と呼ばれるのもわかる気がします。

(2012.6.22撮影)



帽子が取れるのね

まるでたまごの殻を破って出てくるよう
明け方に出だして、伸びて、レースをおろしすぐに大きくなるそうですよ
こ
キヌガサタケは、日本では「コムソウタケ」とも呼ばれているそうで、絶滅危惧種にも指定されている大変珍しいキノコだそうです。胞子は他のキノコと違って虫が運ぶそうです。
初めて見ました。感動です!!!
自然の造形美っていうんでしょうか。レースのスカートをはいています。
「キノコの女王」と呼ばれるのもわかる気がします。

(2012.6.22撮影)



帽子が取れるのね

まるでたまごの殻を破って出てくるよう
明け方に出だして、伸びて、レースをおろしすぐに大きくなるそうですよ
こ
2012年06月18日
◆瓜生の栗の木

瓜生の羅漢さんへの入口にある「栗の木」はものすごい大きいですね。
ビックリしました。
地面にまで枝が着いていますよ。
これは森の大ムクノキ(県指定文化財天然記念物)に匹敵する地域のお宝では・・・
こ
タグ :栗の木
2012年05月10日
◆小河山観音寺の壁画
先日(5/8)の「お宝探検サロン(おたたん)」での話題から
小河の観音にある小河山観音寺
そのお堂の中に襖絵というか壁画というか、大きな墨絵があります。
3羽の鶴と松の木が描かれています。
でも、作者の記載がなく、だれがいつ、何のために描かれたのか分かりません。
(ひょっとして福田眉仙さん?)
どなたかこの画の所以をご存じの方はおられますか。




よく見てみると絵を貼り合わせて作られていますね。所々ずれています。
こ
2011年12月20日
◆能下の「狸塚」

みなさんは能下の北の方、テクノラインの脇に狸の焼き物(信楽焼?)が置かれた「狸塚」があるのをご存知ですか。
「みちしるべ 狸塚」と書かれた立札の裏には、下写真のように

この豊かな自然を畏敬し、調和ある共棲を願う
平成十一年十月 狸篤志一同
聞くと、上のテクノポリスができて、このテクノラインに車が多く通りだすと当時、毎日のように狸が轢かれて死んでいったそうです。そのことに心を痛めた当時のテクノの人たちは有志で、ここに「狸塚」を作ったと聞きます。碑に書かれた「共棲」には、そういった意味が込められていたのですね。当時の人は本当にそう願ったのでしょう。
こういったことも、忘れ去られないように語り継いでいかなければなりません。不可抗力であれ、人間がとった行為にどう向き合い行動するか、そこに人間の真価が問われているように思います。
こ
2011年12月12日
◆たまご石と天狗岩

能下の「たまご石」(別称 巾着岩)(一番上の岩)
岩の下側が紅葉で隠れてしまっていますが

山下の道路が能下を通るテクノライン
テクノラインを相生から播磨科学公園都市(播磨テクノポリス)の方に上っていくと、能下地区でテクノラインの左側に正面が平らで丸い岩があります。能下の八幡神社の前を通って坂道を少し上がると対面してよく見えます。
この岩こそ地元でも知る人ぞ知る岩で、「たまご石」だとか「巾着岩」と呼ばれています。
一方で、テクノラインを上っていくと、先日紅葉で取り上げた森の磐座神社の背後には御神体である権現山がありますが、その山頂付近に尖がった岩が目にとまります。この岩はその形からか「天狗岩」と呼ばれています。
見方によると、「たまご石」と「天狗岩」は谷を挟んで向かい合う格好になっていて、ある人によると、磐座神社は男性を象徴する神社で、天狗岩の天狗はそれこそそうですし、そうするとまあるい「たまご石」は女性だということになって、何か信仰的なものがあったのではないかといわれます。

磐座神社背後の権現山

権現山山頂付近の「天狗岩」
こ
2011年12月05日
◆柿本人麻呂の万葉歌碑
詠黄葉
妻籠矢野神山露霜尓々賓比始散巻惜 (妻籠る矢野の神山露霜ににおひそめたり散らまく惜しも)
朝露尓染始秋山尓鐘礼莫零在渡金 (朝露ににほひそめたる秋山に時雨な降りそあり渡るがね)
右二首柿本朝臣人麻呂之謌集出
森の「磐座(いわくら)神社」には、上記のような、藤原京時代(7世紀後半)の万葉歌人 柿本人麻呂が詠んだといわれる万葉歌碑が立っています。四国産の青自然石でできたその歌碑は、国宝『西本願寺万葉集』より写字されていて、昭和59年(1984)に相生市教育委員会と相生市文学碑設立協会によって建てられました。
その2首は、題字に「黄葉を詠む」とあるように、「矢野の神山」の黄葉の美しさに思いを寄せた歌です。現地の案内板には、「作者は柿本人麻呂と思われる。石見国と大和の往還の途次、たまたまこの磐座神社境内の黄葉を見聞して、感に耐えずこの歌を詠んだもの」と書かれています。
ただ、正確には「矢野の神山」の矢野がどこかというのは確定していませんが、当然私たちの矢野町も有力な候補地としてあり、その場合、人麻呂が詠んだ黄葉は磐座神社の満山黄葉で、神山とは磐座神社の背後の権現山だとされています。ちなみに、磐座神社の磐座とは、神がいる大きな岩という意味です。(相生市ホームページ参照)
では、どれだけ磐座神社の黄葉が美しいか、先日も1枚写真を上げましたが、見てみましょう。




う~ん、すばらしい。これを見ると、人麻呂の詠んだ矢野の神山の黄葉とは、きっと磐座神社の黄(紅)葉に違いないと確信しますね(笑)。
ということで、柿本人麻呂の詠んだ万葉歌を歴史的根拠に、矢野町を全国に知ってもらおうと、そして矢野町の活性化につなげようと、全国的規模の短歌大会を継続して矢野町でできないか、検討始めたところです。
こ
2011年09月22日
◆磐座神社
前回、磐座(いわくら)神社の安産信仰を取り上げましたので、少し磐座神社について調べてみました。
磐座(いわくら)神社は、最初教えられないと「いわくら」とちょっと読めないですね。「磐」は大きな石、「座」は「います」ということで、大きな石に神がいる神社ということだそうです。そういう名前がつくだけあって、磐座神社には巨岩伝説があるようですね。詳しくは、相生市のホームページ(相生の伝説と昔話)に書いてあります(下線部をクリック)。

神社の背後にそびえ立つ権現山と天狗岩
神社の境内に入ると大木が茂り、凛とした静けさのなかに、ここで何百年も行われてきた人々の営みがあり、思いを馳せます。

山上の大きな石に神が降りてきたときに落ちてきたという座光石

四十七士の絵馬

使われなくなった芝居の舞台
ところで、神社の由緒書きには、権現山を神体山として拝したとあります。御神体ですね。権現山のほかにも磐座神社の背後には矢野神山(かみやま)として祇園山(竜王山)と神田山があります。
日本人は、神体山というように山そのものを神とみなしています。山のほかにも、日本人は物そのものにもいのち・価値を認め、崇め、畏れ、敬ってきました。そこから「もったい(勿体)ない」という意識が生まれています。西洋人にはちょっとない感性です。それが自然と人間との調和を育んできました。
ちなみに、精霊崇拝・アニミズムは、そこに神(霊魂)が宿るというように物に精霊がとりつくイメージで、物そのものを神とみなす日本人の感覚とちょっと違うようです。
こ
磐座(いわくら)神社は、最初教えられないと「いわくら」とちょっと読めないですね。「磐」は大きな石、「座」は「います」ということで、大きな石に神がいる神社ということだそうです。そういう名前がつくだけあって、磐座神社には巨岩伝説があるようですね。詳しくは、相生市のホームページ(相生の伝説と昔話)に書いてあります(下線部をクリック)。
神社の背後にそびえ立つ権現山と天狗岩
神社の境内に入ると大木が茂り、凛とした静けさのなかに、ここで何百年も行われてきた人々の営みがあり、思いを馳せます。
山上の大きな石に神が降りてきたときに落ちてきたという座光石
四十七士の絵馬
使われなくなった芝居の舞台
ところで、神社の由緒書きには、権現山を神体山として拝したとあります。御神体ですね。権現山のほかにも磐座神社の背後には矢野神山(かみやま)として祇園山(竜王山)と神田山があります。
日本人は、神体山というように山そのものを神とみなしています。山のほかにも、日本人は物そのものにもいのち・価値を認め、崇め、畏れ、敬ってきました。そこから「もったい(勿体)ない」という意識が生まれています。西洋人にはちょっとない感性です。それが自然と人間との調和を育んできました。
ちなみに、精霊崇拝・アニミズムは、そこに神(霊魂)が宿るというように物に精霊がとりつくイメージで、物そのものを神とみなす日本人の感覚とちょっと違うようです。
こ
2011年09月20日
◆もう一つの安産信仰
以前、矢野町のパワースポットで瓜生の安産杉を紹介しましたが、もう一つ矢野の安産の神様を紹介しましょう。
森の「磐座(いわくら)神社」です。
磐座神社には、県指定の天然記念物「コヤスノキ叢林」があります。叢林とは、樹木が群がって生えている林のことをいいます。コヤスノキは中国地方中部、岡山県東部と西播地方に限って分布する珍しい植物で、五月ごろ新枝の先に淡黄色の花をつけ、秋には直径1cmばかりの球形の実をつけます。


神社の由緒書きには、「中世には安産の守護神であり矢野庄總鎮守の杜として尊信崇敬せらる」とあります。相生市史には、「これは境内に子安の木があり、赤い実の様子から安産信仰が生まれてきたのであろう」と書いてありました。
矢野町は、安産の神様もたくさんいて、緑あふれる自然と人情味のある人たちの中で、子育てにはもってこいだと思いますよ。
こ
森の「磐座(いわくら)神社」です。
磐座神社には、県指定の天然記念物「コヤスノキ叢林」があります。叢林とは、樹木が群がって生えている林のことをいいます。コヤスノキは中国地方中部、岡山県東部と西播地方に限って分布する珍しい植物で、五月ごろ新枝の先に淡黄色の花をつけ、秋には直径1cmばかりの球形の実をつけます。

神社の由緒書きには、「中世には安産の守護神であり矢野庄總鎮守の杜として尊信崇敬せらる」とあります。相生市史には、「これは境内に子安の木があり、赤い実の様子から安産信仰が生まれてきたのであろう」と書いてありました。
矢野町は、安産の神様もたくさんいて、緑あふれる自然と人情味のある人たちの中で、子育てにはもってこいだと思いますよ。
こ
2011年09月07日
◆犬塚五輪塔
先日、約30年前に能下で行われた「犬塚まつり」を取り上げました。
実は、まだ「犬塚」を見たことなかったので今日、見てきました。
テクノラインで三濃山トンネルに入る200mぐらい手前左側にありました(入口がわからず何度も通り過ぎてしまいました)。そこから能下川に架かる櫻橋を渡ってすぐです。

確かに桜の木の下に五輪塔があります。
このちょっとした空間で、約30年前、能下音頭が歌われ踊られたのですね。
地面はその時からもう、アスファルトだったのかな?

秦河勝・三本卒塔婆伝説(犬塚伝説)をもつ五輪塔(鎌倉後期~南北朝期)
でも、よく倒れないでありますよね。先日の台風でも大丈夫だったんですね。
教育委員会の説明文です。

画像をクリックすると大きくなります
こ
実は、まだ「犬塚」を見たことなかったので今日、見てきました。
テクノラインで三濃山トンネルに入る200mぐらい手前左側にありました(入口がわからず何度も通り過ぎてしまいました)。そこから能下川に架かる櫻橋を渡ってすぐです。

確かに桜の木の下に五輪塔があります。
このちょっとした空間で、約30年前、能下音頭が歌われ踊られたのですね。
地面はその時からもう、アスファルトだったのかな?
秦河勝・三本卒塔婆伝説(犬塚伝説)をもつ五輪塔(鎌倉後期~南北朝期)
でも、よく倒れないでありますよね。先日の台風でも大丈夫だったんですね。
教育委員会の説明文です。

画像をクリックすると大きくなります
こ
2011年09月06日
◆源重郎池2
源重郎さんをはじめとする小河の人たち先人が苦労して築いた源重郎池。それは今でも私たちに恵みをもたらしてくれています。
こうして築造され、修理されてきた源重郎池ですが、時の代官や幕府勘定奉行は源重郎さんに対して幾度となく、「自分入用(私財)を以、溜池壱ヶ所取立候」ことは「奇特之儀に付御褒美として銀三枚」というように褒美を遣わせています。また、小河の人たちに対しても庄屋の曾平に「隣郷えも余水分け遣候様骨折世話いたし候段、厚く誉置」くと申し渡しています。
このことに対して、『相生市史』では以下のような見解を示しています。長文ですが重要なポイントですので記します。
「源重郎池の築造や修築事業に対し、歴代の代官や幕府勘定奉行がこれを称賛し、源重郎や小河村名主などに褒美まで遣わしている点は、この事業の一つの特徴といってよい。これらのことを考慮すると、この築池事業は、代官などの領主階級の奨励にもとづいておこなわれたのではないかと推察することもできる。(中略)
本来領主階級は、主体的に灌漑施設の整備に取り組まねばならない筈であった。江戸時代には、村内にある小規模な堤防や橋梁の掛替などは村の自普請によるのが原則ではあったが、「池所の池」のような用水溜池の構築は、村による自普請の範囲を超えたものであり、領主の積極的な施策(普請費用の負担)のもとに実施されるべきであった。領主がそれに対して消極的であるかぎり、旱損場を救うことはできない。
源重郎を中心とする小河村農民は代官たちの施策をじっと待っているわけにはいかず、ついに『当村旱損場ニ付、往々村方一同助ケノため自分入用を以』って『池所の池』、通称源重郎池を構築することになった。この点に源重郎池築造の最大の意義をみいだすことができる」
何もかもを行政に頼ることのできない今の時代に通じるものをどこか感じませんか。
『相生市史』では、結果的に領主に頼らず村人(農民)たちが自分たちの手で源重郎池を築造したことに最大の意義があるといっています。つまり、これこそが「自律した地域」であり、「地域自治」といえましょう。『相生市史』は源重郎池の築造・修復に関して、そこに最大の意義をみいだしているのです。
先人が残した足跡(過去からの伝言)を今の人が受け取り咀嚼し、また後世へとつないでいく、その大切な営みを考えさせられます。今日、小河の活動が国や県から表彰されるのも源重郎池築造・修復当時の小河の人たちの精神を受け継いでいるのかもしれません。
その後、源重郎さんの子孫である光葉久吉氏から「池所の池は、小河村持ちにして貰いたい」と申し出あって、源重郎池は小河村の所有(総有)になったそうです。明治29年(1896)5月、小河村の人たちは「村民相謀リ碑ヲ以テ其ノ徳ヲ表ショウセリ」(『赤穂郡史』(明治の地誌))と、「築池記念碑」を建立し謝恩の一端を表しました(下写真)。

源重郎池築池記念碑(2011年5月9日撮影)
こ
続きを読む
こうして築造され、修理されてきた源重郎池ですが、時の代官や幕府勘定奉行は源重郎さんに対して幾度となく、「自分入用(私財)を以、溜池壱ヶ所取立候」ことは「奇特之儀に付御褒美として銀三枚」というように褒美を遣わせています。また、小河の人たちに対しても庄屋の曾平に「隣郷えも余水分け遣候様骨折世話いたし候段、厚く誉置」くと申し渡しています。
このことに対して、『相生市史』では以下のような見解を示しています。長文ですが重要なポイントですので記します。
「源重郎池の築造や修築事業に対し、歴代の代官や幕府勘定奉行がこれを称賛し、源重郎や小河村名主などに褒美まで遣わしている点は、この事業の一つの特徴といってよい。これらのことを考慮すると、この築池事業は、代官などの領主階級の奨励にもとづいておこなわれたのではないかと推察することもできる。(中略)
本来領主階級は、主体的に灌漑施設の整備に取り組まねばならない筈であった。江戸時代には、村内にある小規模な堤防や橋梁の掛替などは村の自普請によるのが原則ではあったが、「池所の池」のような用水溜池の構築は、村による自普請の範囲を超えたものであり、領主の積極的な施策(普請費用の負担)のもとに実施されるべきであった。領主がそれに対して消極的であるかぎり、旱損場を救うことはできない。
源重郎を中心とする小河村農民は代官たちの施策をじっと待っているわけにはいかず、ついに『当村旱損場ニ付、往々村方一同助ケノため自分入用を以』って『池所の池』、通称源重郎池を構築することになった。この点に源重郎池築造の最大の意義をみいだすことができる」
何もかもを行政に頼ることのできない今の時代に通じるものをどこか感じませんか。
『相生市史』では、結果的に領主に頼らず村人(農民)たちが自分たちの手で源重郎池を築造したことに最大の意義があるといっています。つまり、これこそが「自律した地域」であり、「地域自治」といえましょう。『相生市史』は源重郎池の築造・修復に関して、そこに最大の意義をみいだしているのです。
先人が残した足跡(過去からの伝言)を今の人が受け取り咀嚼し、また後世へとつないでいく、その大切な営みを考えさせられます。今日、小河の活動が国や県から表彰されるのも源重郎池築造・修復当時の小河の人たちの精神を受け継いでいるのかもしれません。
その後、源重郎さんの子孫である光葉久吉氏から「池所の池は、小河村持ちにして貰いたい」と申し出あって、源重郎池は小河村の所有(総有)になったそうです。明治29年(1896)5月、小河村の人たちは「村民相謀リ碑ヲ以テ其ノ徳ヲ表ショウセリ」(『赤穂郡史』(明治の地誌))と、「築池記念碑」を建立し謝恩の一端を表しました(下写真)。
源重郎池築池記念碑(2011年5月9日撮影)
こ
続きを読む
2011年09月05日
◆源重郎池1
源重郎池の石堤(2011年5月9日撮影)
ここにもシカ避けのフェンスが。シカが草を食べて環境を壊すらしい。
先日、小河活動協議会の視察に関して、ブログで小河のまとまりのキーは「源重郎池」にあるようだと書きました。自治会長さんは確かそれを「原点」と言っていたように思います。今回は、源重郎池について「地域自治」の観点から2回に分けて述べてみましょう。
源重郎池は、川が小川で水の少ない小河村にあって用水を確保するために、1800年代前半に同じ小河村の農民である2代目源重郎さんから3代にわたって私財を投じて、集落から約4kmも上った山の中腹に築造した谷池(山の谷を利用して水をためたため池)です。正式には「池所(いけどこ)の池」というそうです。池所は地名です。
記録によると、享和2年(1802)から文化6年(1809)の築造時には、「人足料 銀5貫239匁、諸雑費331匁2分、計銀5貫570匁2分」が源重郎さんによって投じられたということです。これが今ではどれくらいのお金になるかわかりませんが。
私財を投じて集落から約4kmも上がった山中にため池を築くことに思い至った源重郎さんもすごいですが、小河村の人たちや隣村の人たちもすごかったと思います。その時の記録には、「外に合力175人 寅年小河村中110人、上土井村より51人、観音より14人」ともあります。つまり、村総出で8年もの歳月をかけて源重郎池を造ったわけです。
加えて、冒頭の写真を見てください。源重郎池の堤は石積みでできています。これは、谷池としては日本でも珍しいようです。自動車のない時代に、村人は力を合わせて(合力:ごうりき)、重い石をもって約4kmものあるともいえない山道を一歩ずつ何度も上り下りし、石を積み上げていったのです。その光景を思い浮かべると胸にくるものがあります。
また、天保年間(天保3年~6年)の4代目源重郎さんによる大修理では、さすがに源重郎さん家も資金に余裕がなく、小河村の人たちと隣村の人たちは「頼母子講」を起こし、それによって経費を賄ったといいます。
このように、3代にわたる源重郎さんをはじめとする小河の人たちは、自分たちの手で、すなわち自分たちの知恵と汗とお金で村を守り、生活を維持してきたのです。先人たちのおかげで今の私たちがあるわけです。そして、先人たちは私たちに、地域自治とはこういうもんだということを何か教えてくれているような気がします。自治会長さんが、「小河のまとまりの原点が源重郎池にある」といわれるのも納得できます。
こ
続きを読む
2011年09月02日
◆犬塚まつり
一昨日のブログに「矢野音頭」を取り上げました。
すると、それを見てくださった方から情報をいただきました。
矢野音頭の第14番、能下の部分の歌詞
14 能下犬塚花の頃(ヨイヨイ)
咲いた桜の木の下で
踊る音頭の浴衣衆
三本卒塔婆に渦を捲く(サノヨイヨイ)
に関して書かれた記事があるということです。
それは、約30年前の相生ライフで、
『相生ライフ 第25号(昭和57年4月18日)』の「街の話題 "犬塚まつり"」
という記事でした(下画像)。

画想をクリックすると大きくなります
それによると、昭和57年4月11日に能下の方たちが村おこしに「犬塚まつり」を初めて催されたということです。その犬塚まつりの光景が、矢野音頭の能下部分の歌詞になっているという情報でした。犬塚まつりでは、能下の三本卒塔婆にある桜の木の下で「能下音頭」を歌いながら踊ったようですね。
能下音頭
作詞 坂本一郎 作曲 芦田晴夫
ハアー
行こか詣ろか 犬塚さまへ
花も薄紅 パッと咲く
咲いた桜は ワン公のみ霊
今もみあげて ほめそやす
ところで、矢野音頭の作詞者は坂本一路さん、能下音頭の作詞は坂本一郎さん。ひょっとして同じ人物ですか?
ここで、みなさんにお願いです。
もし、この三本卒塔婆の桜の木の下で踊りや花見をしている貴重な写真をお持ちの方がございましたら、一度私、コミュニティ推進員の古賀(090-7821-6544)までご連絡いただけないでしょうか。こういう貴重な写真はそれこそ地域のお宝ですので、よかったらデジタル化してアーカイブに残していけたらと思います。
能下音頭のうたわれたこの当時、能下地区は22戸だったんですね。ちなみに今は自治会資料によるとさらに減って13戸です。
こ 続きを読む
すると、それを見てくださった方から情報をいただきました。
矢野音頭の第14番、能下の部分の歌詞
14 能下犬塚花の頃(ヨイヨイ)
咲いた桜の木の下で
踊る音頭の浴衣衆
三本卒塔婆に渦を捲く(サノヨイヨイ)
に関して書かれた記事があるということです。
それは、約30年前の相生ライフで、
『相生ライフ 第25号(昭和57年4月18日)』の「街の話題 "犬塚まつり"」
という記事でした(下画像)。

画想をクリックすると大きくなります
それによると、昭和57年4月11日に能下の方たちが村おこしに「犬塚まつり」を初めて催されたということです。その犬塚まつりの光景が、矢野音頭の能下部分の歌詞になっているという情報でした。犬塚まつりでは、能下の三本卒塔婆にある桜の木の下で「能下音頭」を歌いながら踊ったようですね。
能下音頭
作詞 坂本一郎 作曲 芦田晴夫
ハアー
行こか詣ろか 犬塚さまへ
花も薄紅 パッと咲く
咲いた桜は ワン公のみ霊
今もみあげて ほめそやす
ところで、矢野音頭の作詞者は坂本一路さん、能下音頭の作詞は坂本一郎さん。ひょっとして同じ人物ですか?
ここで、みなさんにお願いです。
もし、この三本卒塔婆の桜の木の下で踊りや花見をしている貴重な写真をお持ちの方がございましたら、一度私、コミュニティ推進員の古賀(090-7821-6544)までご連絡いただけないでしょうか。こういう貴重な写真はそれこそ地域のお宝ですので、よかったらデジタル化してアーカイブに残していけたらと思います。
能下音頭のうたわれたこの当時、能下地区は22戸だったんですね。ちなみに今は自治会資料によるとさらに減って13戸です。
こ 続きを読む
2011年08月31日
◆矢野音頭
今日で8月も終わりですね。
ということは子どもたちの夏休みも終わりです。宿題は終わったかな。
外は、まだじっとり暑いですね。
でも、体で感じとる風は心地よく、秋を感じさせます。
「いぶき」の駐車場ではトンボがいっぱい舞っていますよ。
さて、先の「矢野町ふれあい納涼祭」では同好会のみなさんが「矢野音頭」を歌われました。
矢野音頭は、1987年(昭和62年)に地元地域、能下の坂本一路さんによって作詞され、不朽の名曲九州炭坑節にのせて歌われます。
矢野音頭は、三濃山村も含む矢野町の全15集落について歌われていますので、集落の紹介をかねて矢野音頭の歌詞を下に載せましょう。
炭坑節「矢野音頭」
詞 坂本一路 曲 炭坑節拝借
1 瓜生よいとこ羅漢さん(ヨイヨイ)
岩と紅葉に囲まれて
十六羅漢がおわします
ほんに羅漢はよいところ(サノヨイヨイ)
2 上は矢野町の真ん中で(ヨイヨイ)
天満神社みそなわす
ご遺徳みんなで慕うなら
上の町中に花が咲く(サノヨイヨイ)
3 町は菅谷よいところ(ヨイヨイ)
お寺教順名の通り
雨が降ろうが風吹こが
今日も平和の鐘が鳴る(サノヨイヨイ)
4 町は二っ木昔から(ヨイヨイ)
赤い紅葉で名が高い
京明地蔵にぬかずけば
みんなニコ〃繁昌する(サノヨイヨイ)
5 真広よいとこ薬師さん(ヨイヨイ)
東山からよい便り
佛のみ教えを信ずれば
心はいつも日本晴れ(サノヨイヨイ)
6 下田よいとこ矢野川の(ヨイヨイ)
清い流れの傍らで
お寺明専古くから
今日も感謝の法を説く(サノヨイヨイ)
7 偉い人なら上土井よ(ヨイヨイ)
初代村長山島さん
学徳秀れて今も尚
仰ぐみんながまた偉い(サノヨイヨイ)
8 小河観音誰も知る(ヨイヨイ)
浅野殿様信仰寺
家老大石庭に立ち
盡きぬ名残りを留めてる(サノヨイヨイ)
9 森の名所は市の名所(ヨイヨイ)
お寺おう椋おう社
感状山を仰いでは
コヤスの木々もほめている(サノヨイヨイ)
10 中野よい人よい田圃(ヨイヨイ)
朝は早よから日暮れまで
今日も照りますお日さまは
みんな感謝の手を合わす(サノヨイヨイ)
11 金が坂から金坂に(ヨイヨイ)
人は純情で勤勉で
みんな笑顔で今日もまた
明日の金坂夢に抱く(サノヨイヨイ)
12 釜出よいとこ蛍狩り(ヨイヨイ)
清い流れに清い石
みんな仲良く手を握るや
岸の蛍も身を焦がす(サノヨイヨイ)
13 榊よいとこ信の町(ヨイヨイ)
法林西教古い寺
今日もみんなが手を合わしや
広い町中もパラダイス(サノヨイヨイ)
14 能下犬塚花の頃(ヨイヨイ)
咲いた桜の木の下で
踊る音頭の浴衣衆
三本卒塔婆に渦を捲く(サノヨイヨイ)
15 三濃が山からお呼び声(ヨイヨイ)
千手観音山が手を招く
衆生可愛やいとおしや
今日も山から呼んでいる(サノヨイヨイ)

こ
ということは子どもたちの夏休みも終わりです。宿題は終わったかな。
外は、まだじっとり暑いですね。
でも、体で感じとる風は心地よく、秋を感じさせます。
「いぶき」の駐車場ではトンボがいっぱい舞っていますよ。
さて、先の「矢野町ふれあい納涼祭」では同好会のみなさんが「矢野音頭」を歌われました。
矢野音頭は、1987年(昭和62年)に地元地域、能下の坂本一路さんによって作詞され、不朽の名曲九州炭坑節にのせて歌われます。
矢野音頭は、三濃山村も含む矢野町の全15集落について歌われていますので、集落の紹介をかねて矢野音頭の歌詞を下に載せましょう。
炭坑節「矢野音頭」
詞 坂本一路 曲 炭坑節拝借
1 瓜生よいとこ羅漢さん(ヨイヨイ)
岩と紅葉に囲まれて
十六羅漢がおわします
ほんに羅漢はよいところ(サノヨイヨイ)
2 上は矢野町の真ん中で(ヨイヨイ)
天満神社みそなわす
ご遺徳みんなで慕うなら
上の町中に花が咲く(サノヨイヨイ)
3 町は菅谷よいところ(ヨイヨイ)
お寺教順名の通り
雨が降ろうが風吹こが
今日も平和の鐘が鳴る(サノヨイヨイ)
4 町は二っ木昔から(ヨイヨイ)
赤い紅葉で名が高い
京明地蔵にぬかずけば
みんなニコ〃繁昌する(サノヨイヨイ)
5 真広よいとこ薬師さん(ヨイヨイ)
東山からよい便り
佛のみ教えを信ずれば
心はいつも日本晴れ(サノヨイヨイ)
6 下田よいとこ矢野川の(ヨイヨイ)
清い流れの傍らで
お寺明専古くから
今日も感謝の法を説く(サノヨイヨイ)
7 偉い人なら上土井よ(ヨイヨイ)
初代村長山島さん
学徳秀れて今も尚
仰ぐみんながまた偉い(サノヨイヨイ)
8 小河観音誰も知る(ヨイヨイ)
浅野殿様信仰寺
家老大石庭に立ち
盡きぬ名残りを留めてる(サノヨイヨイ)
9 森の名所は市の名所(ヨイヨイ)
お寺おう椋おう社
感状山を仰いでは
コヤスの木々もほめている(サノヨイヨイ)
10 中野よい人よい田圃(ヨイヨイ)
朝は早よから日暮れまで
今日も照りますお日さまは
みんな感謝の手を合わす(サノヨイヨイ)
11 金が坂から金坂に(ヨイヨイ)
人は純情で勤勉で
みんな笑顔で今日もまた
明日の金坂夢に抱く(サノヨイヨイ)
12 釜出よいとこ蛍狩り(ヨイヨイ)
清い流れに清い石
みんな仲良く手を握るや
岸の蛍も身を焦がす(サノヨイヨイ)
13 榊よいとこ信の町(ヨイヨイ)
法林西教古い寺
今日もみんなが手を合わしや
広い町中もパラダイス(サノヨイヨイ)
14 能下犬塚花の頃(ヨイヨイ)
咲いた桜の木の下で
踊る音頭の浴衣衆
三本卒塔婆に渦を捲く(サノヨイヨイ)
15 三濃が山からお呼び声(ヨイヨイ)
千手観音山が手を招く
衆生可愛やいとおしや
今日も山から呼んでいる(サノヨイヨイ)
こ
2011年08月24日
◆三濃山登山-ムラの跡
三濃山村は昭和50年代に最後の一家が離村して廃村となりました。あれから約40年、ムラの跡はどうなっているのでしょう。元住民のTさんに案内してもらい、ぐるっと回ってみました。
家はすべて朽ち果てて無くなり、田や畑であったところは大木や竹が生え、シダが生い茂り、森化しています。それは住民がムラを下りられるとき、田畑に植林されて離村されたことにもよります。
かつてここにムラが存在し人の生活があったこと、そしてきれいな棚田の風景があったことが嘘のようです。30年以上という時の流れを思わずにはおられません。棚田のあるムラの風景を見られなかったのが残念です。

もともと畑だったのでしょうか。シダが覆っています。

田の中に大木が育っています

ここにも

石垣の上には家が建っていました。もうありません。

家があった場所は竹林に

家を感じさせるものは、壊れた瓦ぐらい

座敷のあった真ん中に巨木が・・・30年という年月

井戸の跡

井戸横にある水溜め場
この時期オタマジャクシがうようよいました
それだけ水温が低いのですね

別の水溜め場

農業施設であったため池の跡
三濃山は、歴史的にも高麗の僧 恵弁・恵聡が逃れてやってきた地、また聖徳太子の側近、秦河勝が狩りを楽しんだ地、そしてそういう仏縁浅からぬ地に空海が寺院を建立しようとやってきた地と伝えられています。
後世に、秦内麻呂が河勝の遺蹟を訪ね偲び求福教寺を興し、その後、源義家が堂宇を再興して三濃千坊といわれるまで一時栄えました。ちなみに、求福教寺観音堂の本尊は千手観世音菩薩像で、向かって右に金龍に乗った弘法大師(空海)像、左に聖徳太子像が祭られています。だた、実際この地にムラができたのは江戸時代以降だろうといわれています。
そんな歴史上の大物が多数関わってきた三濃山。それこそ地域の宝ですし、それを放っておくわけにはいかないでしょう。地域の活性化、すなわち矢野町の活性化や元気に十分貢献できるパワーを三濃山は秘めていると思うのです。
昨日のブログにも書きましたが、今、大阪の篤志家一家とわずかな有志によって三濃山はなんとか維持されている状態で、元住民のお一人は申し訳ない気持ちだといわれます。三濃山村の土地権利も、時代的に他の山林同様どうしようもできず、大部分は元住民が今でもそのままもっておられるようです。
今、三濃山を地域の宝、矢野町の宝と捉えるならば、地域としてなんとか三濃山を管理・運営できないものだろうか。しんどいだけでは続きませんので、地域事業としてそこを舞台に地域がお金を稼げる事業ができないだろうか。
個人的な思いをいえば、将来的には、田畑・住居のあった森化した部分も、もう一度切り開いてなんらかの事業展開につなげられたらと、そんなことを思ったりしています。
こ
家はすべて朽ち果てて無くなり、田や畑であったところは大木や竹が生え、シダが生い茂り、森化しています。それは住民がムラを下りられるとき、田畑に植林されて離村されたことにもよります。
かつてここにムラが存在し人の生活があったこと、そしてきれいな棚田の風景があったことが嘘のようです。30年以上という時の流れを思わずにはおられません。棚田のあるムラの風景を見られなかったのが残念です。
もともと畑だったのでしょうか。シダが覆っています。
田の中に大木が育っています
ここにも

石垣の上には家が建っていました。もうありません。
家があった場所は竹林に
家を感じさせるものは、壊れた瓦ぐらい
座敷のあった真ん中に巨木が・・・30年という年月
井戸の跡
井戸横にある水溜め場
この時期オタマジャクシがうようよいました
それだけ水温が低いのですね
別の水溜め場
農業施設であったため池の跡
三濃山は、歴史的にも高麗の僧 恵弁・恵聡が逃れてやってきた地、また聖徳太子の側近、秦河勝が狩りを楽しんだ地、そしてそういう仏縁浅からぬ地に空海が寺院を建立しようとやってきた地と伝えられています。
後世に、秦内麻呂が河勝の遺蹟を訪ね偲び求福教寺を興し、その後、源義家が堂宇を再興して三濃千坊といわれるまで一時栄えました。ちなみに、求福教寺観音堂の本尊は千手観世音菩薩像で、向かって右に金龍に乗った弘法大師(空海)像、左に聖徳太子像が祭られています。だた、実際この地にムラができたのは江戸時代以降だろうといわれています。
そんな歴史上の大物が多数関わってきた三濃山。それこそ地域の宝ですし、それを放っておくわけにはいかないでしょう。地域の活性化、すなわち矢野町の活性化や元気に十分貢献できるパワーを三濃山は秘めていると思うのです。
昨日のブログにも書きましたが、今、大阪の篤志家一家とわずかな有志によって三濃山はなんとか維持されている状態で、元住民のお一人は申し訳ない気持ちだといわれます。三濃山村の土地権利も、時代的に他の山林同様どうしようもできず、大部分は元住民が今でもそのままもっておられるようです。
今、三濃山を地域の宝、矢野町の宝と捉えるならば、地域としてなんとか三濃山を管理・運営できないものだろうか。しんどいだけでは続きませんので、地域事業としてそこを舞台に地域がお金を稼げる事業ができないだろうか。
個人的な思いをいえば、将来的には、田畑・住居のあった森化した部分も、もう一度切り開いてなんらかの事業展開につなげられたらと、そんなことを思ったりしています。
こ
2011年08月23日
◆三濃山登山-求福教寺
かつて三濃山は村落として存在していました。相生市史によると明治末期には17戸70名の方が住まれていました。しかし、時の流れとともに住民は次第に山から下り、昭和50年代に最後の1戸2名が下りて廃村となりました。
そんな三濃山村ですが、毎月18日に大阪よりこられて、求福教寺の観音堂をはじめ境内を清掃され、お経を上げてお参りされている一家があります。そこに相生市内の地域の方や元住民の方が数人加わってお手伝いをされています。

仏具を外に出し観音堂のお掃除をします
境内の掃き掃除もされています

お掃除が終わるとお花とお供え物が供えられ、みんなでお経が上げられます
お話を伺いますと、大阪より来られている一家は、大阪に本社を構え東南アジアに工場を持って帽子の企画・製造を手掛ける会社の社長さんとその兄弟の一家だそうです。もともとは今の社長さんのお父さん、先代が上郡の金出地で事業を始めるとき、事業成功の祈願を行った際に神官から「あの方向から何かを感じる。むしろあちらをまつりなさい」というお告げあったそうです。
それで、その方向は三濃山だったので地元の人に連れて行ってもらうと、先代がそこで見たものは草が生え、荒れ果てた求福教寺だったわけです。信仰心の厚かった先代は私財を費やして観音堂を修復し、また森化していた伽藍跡を切り開き礎石を頼りに山王権現を復元していきました。手前の三重塔もゆくゆくは復元し伽藍を復興させたいと思われていたようです。
その先代も約15年前に亡くなり、今は現社長である息子さんたちが後を引き継いで自分たちの息子さんも一緒に一族で毎月18日にお世話をしに大阪からこられているというわけです。これは並大抵のことではないと思いました。
みなさんはお経が終わると、別に休憩所が建てられているのでそこでお昼をしてから帰られます。このとき、私も神戸新聞の記者さんもお昼を用意していなかったのですが、自分たちのお弁当から少しずつ分けてくださったのでした。そして帰りにはお下がりもいただいて、本当に恐縮です。
毎月来られているという三濃山の元住民の方に「自分が生まれ育ったこの地にやっぱり何か思いがあってこられていますか」と尋ねますと、「それより、(本来自分たちがしなければならない)この地の面倒を見てもらっているので申し訳ないという気持ちがあって…」と答えられました。これは地域づくりの観点からもなかなか意味深い回答です。またあらためて考えてみることとしましょう。

観音堂の向かって右側にある大避神社。秦河勝が祭神

観音堂の向かって左側にある弁財天を祭った市杵嶋神社。弁財天は水の神様

伽藍復元で建てられた山王権現
祭神は山嶽を支配する大山津見の神で、観世音菩薩の権現
山王権現の鳥居だけは昭和3年に菅谷の鳥居屋敷に再建されている

伽藍の中に新たに水子地蔵が作られている

2011年8月23日神戸新聞
こ
続きを読む
そんな三濃山村ですが、毎月18日に大阪よりこられて、求福教寺の観音堂をはじめ境内を清掃され、お経を上げてお参りされている一家があります。そこに相生市内の地域の方や元住民の方が数人加わってお手伝いをされています。
仏具を外に出し観音堂のお掃除をします
境内の掃き掃除もされています
お掃除が終わるとお花とお供え物が供えられ、みんなでお経が上げられます
お話を伺いますと、大阪より来られている一家は、大阪に本社を構え東南アジアに工場を持って帽子の企画・製造を手掛ける会社の社長さんとその兄弟の一家だそうです。もともとは今の社長さんのお父さん、先代が上郡の金出地で事業を始めるとき、事業成功の祈願を行った際に神官から「あの方向から何かを感じる。むしろあちらをまつりなさい」というお告げあったそうです。
それで、その方向は三濃山だったので地元の人に連れて行ってもらうと、先代がそこで見たものは草が生え、荒れ果てた求福教寺だったわけです。信仰心の厚かった先代は私財を費やして観音堂を修復し、また森化していた伽藍跡を切り開き礎石を頼りに山王権現を復元していきました。手前の三重塔もゆくゆくは復元し伽藍を復興させたいと思われていたようです。
その先代も約15年前に亡くなり、今は現社長である息子さんたちが後を引き継いで自分たちの息子さんも一緒に一族で毎月18日にお世話をしに大阪からこられているというわけです。これは並大抵のことではないと思いました。
みなさんはお経が終わると、別に休憩所が建てられているのでそこでお昼をしてから帰られます。このとき、私も神戸新聞の記者さんもお昼を用意していなかったのですが、自分たちのお弁当から少しずつ分けてくださったのでした。そして帰りにはお下がりもいただいて、本当に恐縮です。
毎月来られているという三濃山の元住民の方に「自分が生まれ育ったこの地にやっぱり何か思いがあってこられていますか」と尋ねますと、「それより、(本来自分たちがしなければならない)この地の面倒を見てもらっているので申し訳ないという気持ちがあって…」と答えられました。これは地域づくりの観点からもなかなか意味深い回答です。またあらためて考えてみることとしましょう。
観音堂の向かって右側にある大避神社。秦河勝が祭神
観音堂の向かって左側にある弁財天を祭った市杵嶋神社。弁財天は水の神様
伽藍復元で建てられた山王権現
祭神は山嶽を支配する大山津見の神で、観世音菩薩の権現
山王権現の鳥居だけは昭和3年に菅谷の鳥居屋敷に再建されている
伽藍の中に新たに水子地蔵が作られている
最後に神戸新聞さんの記事を載せておきます。
(画像をクリックすると大きくなります)
(画像をクリックすると大きくなります)

2011年8月23日神戸新聞
こ
続きを読む
2011年08月22日
◆三濃山登山-アカガシ
去る18日、はじめて 三濃山 に登ってきました。
毎月18日に三濃山求福教寺観音堂をはじめ境内を掃除をされ、お経をあげに遠く大阪から来られる方たち(一家)がおられます。神戸新聞さんがその方たちを取材されるということで、私にも声をかけてくださり一緒させていただきました。
その日に合わせて、もともと三濃山に住まれていた方や相生市の地域の方も登られてお手伝いをされています。今回はその方らについて、私たちはテクノの貯水池方面から登って行きました。テクノ方面からが時間的にも一番登りやすいとのことです。ちなみに観音堂等のお世話をされている一家は、上郡町の金出地から軽の四駆で登ってこられます。

地域の方について登ります。どっちの方向でここが道やといわれても初心者の私にはわかりませんでした。本当に助かりました。ありがとうございました。
頂上に到着です。瀕死のアカガシの木がありました。

このアカガシがかつて元気なときは、相生の那波からも確認できて相生のシンボルのようだったそうです。それが十年以上前から枯れだし、それを何とか食い止めようと地元住民を中心とした有志による「守る会」が1999年に結成され、寄付金を集め樹木医を呼んで見てもらったり、イベントを開催したり、保護活動をしました。
基本的に山頂の水不足が原因のようで、雨の水を貯める装置を作ったり、木々を植えたりして水を何とか確保する処置が施されています。
あれから10年余り。今の状態が上の写真です。なかなか好転したとはいえませんが、アカガシはまだ頑張っていました。当時立てられた表示板には、下の写真のように書かれていました(クリックすると大きくなります)。地域の人たちの思いが伝わってきます。

ちなみに、この山頂の山は「経納山(きょうのうさん)」と呼ばれ、アカガシのそばには秦河勝の遺徳をしのぶお経が納められているといいます。

山頂から見る相生市の風景。この写真ではよくわかりませんが、ここから矢野荘-現相生市ほぼ全域が一望できます。その意味でも三濃山は相生市にとってもシンボルですし、これでアカガシがもし復活したらすごいのにね。
手前の木たちは、「守る会」の人たちによって水を蓄えるために植えられた木々だそうですが、彼ら自身もきつそうです。
三濃山登山レポート、続きます。
こ
毎月18日に三濃山求福教寺観音堂をはじめ境内を掃除をされ、お経をあげに遠く大阪から来られる方たち(一家)がおられます。神戸新聞さんがその方たちを取材されるということで、私にも声をかけてくださり一緒させていただきました。
その日に合わせて、もともと三濃山に住まれていた方や相生市の地域の方も登られてお手伝いをされています。今回はその方らについて、私たちはテクノの貯水池方面から登って行きました。テクノ方面からが時間的にも一番登りやすいとのことです。ちなみに観音堂等のお世話をされている一家は、上郡町の金出地から軽の四駆で登ってこられます。
地域の方について登ります。どっちの方向でここが道やといわれても初心者の私にはわかりませんでした。本当に助かりました。ありがとうございました。
頂上に到着です。瀕死のアカガシの木がありました。
このアカガシがかつて元気なときは、相生の那波からも確認できて相生のシンボルのようだったそうです。それが十年以上前から枯れだし、それを何とか食い止めようと地元住民を中心とした有志による「守る会」が1999年に結成され、寄付金を集め樹木医を呼んで見てもらったり、イベントを開催したり、保護活動をしました。
基本的に山頂の水不足が原因のようで、雨の水を貯める装置を作ったり、木々を植えたりして水を何とか確保する処置が施されています。
あれから10年余り。今の状態が上の写真です。なかなか好転したとはいえませんが、アカガシはまだ頑張っていました。当時立てられた表示板には、下の写真のように書かれていました(クリックすると大きくなります)。地域の人たちの思いが伝わってきます。

ちなみに、この山頂の山は「経納山(きょうのうさん)」と呼ばれ、アカガシのそばには秦河勝の遺徳をしのぶお経が納められているといいます。
山頂から見る相生市の風景。この写真ではよくわかりませんが、ここから矢野荘-現相生市ほぼ全域が一望できます。その意味でも三濃山は相生市にとってもシンボルですし、これでアカガシがもし復活したらすごいのにね。
手前の木たちは、「守る会」の人たちによって水を蓄えるために植えられた木々だそうですが、彼ら自身もきつそうです。
三濃山登山レポート、続きます。
こ




 地域ブログサイト
地域ブログサイト